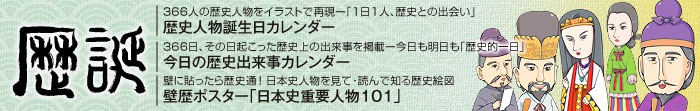

- れきたん歴史人物伝は、歴史上の有名人の誕生日と主な歴史的な出来事を紹介するコーナーです。月に一回程度の割合で更新の予定です。バックナンバーはこのページの最後にまとめてあります。
6月号 2005年6月16日更新 - 【今月の歴史人物】
- 知名度抜群のヒーロー「水戸黄門」
徳川光圀
寛永5(1628).6.10〜- 元禄13(1700).12.6
- 今月号のイラスト
 ◆黄金戦隊は印篭担当かポージング担当かで運命が別れそうな予感。
◆黄金戦隊は印篭担当かポージング担当かで運命が別れそうな予感。
- (C) イラストレーション:結木さくら
- 6月の主な誕生人物
- 01日 カルノー/物理学者
02日 エルガー/作曲家
03日 佐佐木信綱/歌人
04日 ケネー/経済学者、医者
05日 ケインズ/経済学者
06日 ブラウン/物理学者
07日 梅田雲浜/江戸時代の儒者
08日 シューマン/作曲家
09日 滝沢馬琴/江戸時代の読本作者
10日 徳川光國/江戸時代の水戸藩主
11日 シュトラウス/作曲家
12日 花井卓蔵/弁護士
13日 ヤング(トマス)/- 物理学者、医学者、考古学者
14日 クーロン/物理学者
15日 空海/平安時代の僧
16日 荻原井泉水/俳人
17日 クルックス/物理学者、化学者
18日 モース/動物学者
19日 パスカル/- 数学者、物理学者、哲学者
20日 ホプキンズ/生化学者
21日 サルトル/- 哲学者、小説家、劇作家
22日 フンボルト/言語学者、政治家
23日 水野忠邦/江戸時代の老中
24日 ビアス/小説家、ジャーナリスト
25日 ガウディ/建築家
26日 木戸孝允/政治家、幕末の志士
27日 小泉八雲/文学者
28日 ルソー/思想家
29日 黒田清輝/画家
30日 サトー/外交官 - 知名度抜群のヒーロー「水戸黄門」
「この紋所が目に入らぬか!」
テレビやお芝居で現在も愛されるヒーロー、水戸黄門。もちろん創作されたキャラクターではなく、江戸時代の歴史人物・徳川光圀をモデルとしています。日本中を旅し、悪人を改心させて回った黄門さま。さて、その実像はどんなものだったのでしょう。若き日は「かぶき者」
水戸黄門こと徳川光圀は寛永5(1628)年6月10日に、初代水戸藩主徳川頼房の三番目の子として誕生しました。三番目の子ですから普通は家を継ぐことはないのですが、光圀の場合は六歳の時、兄の頼重を差し置いて嗣子と定められます。非常な秀才を発揮したためと記録されているものの、六歳の子が兄を超えて嗣子と定められることはかなりの異常事態とも言え、そのはっきりした理由は分かりません。また、その後光圀は頼重の子を自らの養子とし、後を継がせることで水戸の血筋を兄へと返しています。
嗣子とされた光圀でしたが、十代の頃には「かぶき者」として鳴らしたと伝えられます。「かぶき者」とは奇抜な服装や行動を好む人のことを言い、今で言えば光圀は「ぐれていた」ということでしょうか。正義の味方・黄門様がぐれていたというのはなかなか衝撃的です。お世継ぎとしてのプレッシャーもあったのかもしれません。
ところが、ぐれていた光圀を一変させる出来事が起こります。中国の歴史書『史記』との出会いです。この『史記』中の「伯夷伝」に感銘を受け、以後勉学に励むようになるのです。多くの学者を招いて学問を教わったり、当時一流の大学者であった林羅山とも交友を持ちました。ここから光圀は「名君」への道を歩み始めるのです。藩をあげての大事業
学問に目覚めた光圀は特に歴史をテーマにした書物を数多く編纂しました。中でも名高いのが『大日本史』。明暦3(1657)年に江戸に支局を開設し、これを後に彰考館と名付けて編纂を行いました。『大日本史』は光圀が生きている間には完成せず、水戸藩をあげての大事業としてその死後も編纂が継続されました。江戸の中期ごろには大体の形が出来上がるのですが、それでも手が加え続けられ、結局全てが完成したのは1906(明治39)年。もちろん江戸幕府も水戸藩も存在していませんから、のん気な話と言えばのん気な話でした。
しかし、この250年にもおよぶ大事業は、尊王思想や国家思想を尊ぶ水戸学と呼ばれる学風を形成しました。この水戸学は幕末の尊王攘夷思想にも大きな影響を与えました。桜田門外の変や天狗党の乱など、維新の動乱期には水戸藩と藩出身者が多く登場します。光圀の思想・事業が遠く時を超えて人々を動かしたとすれば、歴史のつながりというものに思いを馳せずにはいられません。
ちなみに、彰考館には数多くの学者が集められ、『大日本史』の編纂が行われていましたが、彼らの中に安積澹泊、佐々十竹という学者がいました。二人とも彰考館の総裁までつとめた優秀な学者であったのですが、澹泊はまたの名を覚兵衛、十竹はまたの名を介三郎といいます。そう、覚さんと介さんです。この二人、字こそ違っていますが、あの助さん格さんのモデルと言われています。名君・徳川光圀
光圀は歴史事業のみならず、藩政の充実にも尽力しました。経済政策から福祉、軍事まで光圀が着手した分野は数多くあります。中には効果をあげられなかった政策もありましたが、光圀の施策がスタート直後の水戸藩の体制を整えたのは間違いないことで、民衆の支持も勝ち取りました。やがて光圀は兄の子・綱条(つなえだ)に家督を譲り、藩主の座を降ります。
政治や学問以外のことでも、光圀に関するエピソードがいくつか残っています。「貧乏で困っている百姓に薬や食べ物を与えた」など、光圀の人格者ぶりを伝えたものも数多く、真偽のほどは別として、こうしたエピソードが名君としての光圀像を形づくる助けとなりました。
「水戸黄門」のお話が「水戸黄門漫遊記」として成立したのは明治の終りごろ、大阪の講談界においてと言われています。光圀が実際に日本全国を歩き回ったことはないようですが、『大日本史』の資料収集のために関東近辺を旅行したことはあったようです。その業績やエピソードが後世においてミックスされ、現在まで愛される時代劇の大ヒーロー「水戸黄門」誕生へとつながったのです。
ホーム|歴誕カレンダーとは|Web歴誕カレンダー|歴誕通販|れきたんQ&A|個人情報について|通信販売表示
れきたん歴史人物伝|れきたん編集室|れきたん壁紙|リンク|お問い合せ
Copyright (C) 2005 有限会社 秋山ワークス