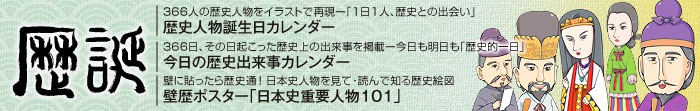

- れきたん歴史人物伝は、歴史上の有名人の誕生日と主な歴史的な出来事を紹介するコーナーです。月に一回程度の割合で更新の予定です。バックナンバーはこのページの最後にまとめてあります。
3月号 2006年3月24日更新 - 【今月の歴史人物】
- 時代に散った志士
- 橋本左内
天保5(1834)3.11〜安政6(1859)10.7
- 今月号のイラスト

- ◆日本、開け黒ゴマ!
- (C) イラストレーション:結木さくら
- 3月の主な誕生人物
- 01日 芥川龍之介/小説家
02日 米内光政/軍人
03日 ベル/発明家
04日 賀茂真淵/江戸時代の国学者
05日 メルカトル/地図学者
06日 ミケランジェロ/画家、彫刻家、建築家
07日 中江藤樹/江戸時代の儒者
08日 平賀譲/造船学者
09日 ミラボー/政治家
10日 マルピーギ/医学者
11日 橋本左内/幕末の学者、思想家
12日 キルヒホッフ/物理学者
13日 高村光太郎/詩人、彫刻家
14日 アインシュタイン/物理学者
15日 ベーリング/医学者
16日 オーム/物理学者
17日 ダイムラー/機械技術者
18日 ラ・ファイエット夫人/小説家
19日 リヴィングストン/探検家、宣教師
20日 前原一誠/志士、政治家
21日 バッハ(J.S.)/作曲家
22日 ファンダイク/画家
23日 マルタン・デュ・ガール/小説家
24日 モリス/工芸家、詩人
25日 樋口一葉/小説家
26日 今東光/小説家
27日 レントゲン/物理学者
28日 コメニウス/神学者、教育学者
29日 平野国臣/幕末の志士
30日 ゴヤ/画家
31日 デカルト/哲学者、数学者 - 時代に散った志士
江戸・幕末の混乱期。激動の時代を生き抜いた人々が新しい時代を作っていったその一方で、若くして散ってしまった人物達が数多くありました。坂本竜馬、吉田松陰、高杉晋作、近藤勇…死因も、思想もさまざまですが、彼らもやはり、新時代の礎であったに違いありません。そんな若くして亡くなった傑物の一人・橋本左内を今回はご紹介します。
稚心を去る
橋本左内は天保5(1834)年3月11日、福井藩にて産まれました。藩医の子です。
幼い頃から類まれな学問の才能を発揮したらしく、15歳にして「啓発録」という文章を書いています。「啓発録」は自らの生きる指針などを書き連ねた書でした。「稚心を去る」「立志」「朋友を択ぶ」といった五項目がしっかりとした文章の中にまとめられています。15の少年が「稚心を去る(幼稚な心を捨てる)」「朋友を択ぶ(親友を選ぶ)」とはなかなか言えるものではありません。早熟で真面目な人となりが浮かび上がってきます。
16の歳に左内は大阪へと出て、緒方洪庵の適塾へと入塾します。緒方洪庵は蘭方医・蘭学者で、種痘を広めることなどに尽力した大人物。適塾はその洪庵が開いた蘭学塾で、あの福沢諭吉もここから巣立ったのです。
左内は適塾で蘭方医学と蘭学を修め、やがて福井藩へと帰りました。福井藩では家督を継いで藩医となり、嘉永5(1854)年に今度は江戸に遊学して洋学を修めました。
大阪、江戸への遊学を通じて左内が得たものはこの上なく大きかったと推察されます。海外の学問を知ることで、世界の情勢にも通じてきます。それらは、左内の心を強く刺激したに違いありません。数々の俊英に囲まれたことも左内を大きく成長させたということもあるでしょう。江戸への遊学期には西郷隆盛とも親交を持ち、意気投合したようです。
こうして西洋の政治体制や文化、経済、教育、軍事などのことを知った左内は、自らも政治のこと、日本のことについて考えるようになるのです。政治手腕を発揮
江戸から福井へと帰った左内は藩校の学監心得というポストにつきます。そこでの左内の活躍は大したものでした。重臣らと協力して藩の教育改革や組織改革、政治改革などに次々と着手したのです。この時の左内はまだ二十代前半。驚異的な手腕と言えます。
やがて左内は藩主松平慶永の付き人として再び江戸へと上ることになりました。いよいよ中央の政治とも関わってゆくわけです。ペリー来航以来混乱していた幕政の中にあって、左内の考え方は開国派でした。具体的にはイギリスと距離を置いてロシア、アメリカと手を結ぶべきというものです。国内的にはさまざまな階層の人が政治に参加できるよう幕政を改革し、やがては富国強兵を実現すべきとしています。君主制と議会制を合わせたような政治体制を模索していたということあり、当時にあってはなかなか先見的なだったと言えるでしょう。将軍継嗣問題と安政の大獄
さて、当時最も重要な問題の一つに将軍継嗣問題というものがありました。当時の将軍は十三代家定でしたが、その後継に挙がっていた人物は二人。徳川慶福(のちの十四代家茂)と一橋慶喜(のちの十五代慶喜)です。ペリー来航問題、条約調印問題といった政治問題も重なり、幕政は混乱の極みに達していたと言っても過言ではありません。左内もこの流れの中に立ち、慶喜派の一人として運動を展開していました。
しかし、十四代将軍となったのは慶福の方でした。慶福を推す幕府の大物、井伊直弼が大老に就任し、その権力によって継嗣問題を決着させたのです。
ところが話はこれでは終わりません。勢いを得た井伊直弼は、慶喜派と当時彼が進めていた施策・日米修好通商条約調印に反対した人々をまとめて処分し始めたのです。これが世に言う安政の大獄です。
安政の大獄は苛烈な弾圧でした。慶喜、そして松平慶永を含む慶喜派の藩主らは謹慎などを命じられ、身分の低い者は死刑となりました。左内は、そこに含まれていました。罪状はまさに「低い身分にも関わらず幕政に介入したこと」でした。左内、刑死。なんと26歳のことです。若くして散る
左内らを処断した井伊直弼は、左内の死後わずか半年の後に桜田門外にて暗殺されました。十四代家茂は早世し、慶喜が十五代将軍となったことはご存知の通りです。左内を死に追いやったことごとくが中途半端なまま消えてしまった形ですが、これもまた歴史の常と言えるでしょう。
それにしても26歳です。江戸期ですから数え年であり、満年齢では25歳。幕末史に名を残した志士達の中には、二十歳そこそこから活躍していた人物は少なくありません。志士達は若者だったというイメージはありますが、そのイメージ以上に彼らは若かったのです。
15歳という若さで「稚心を去る」「立志」と書いた左内。早熟ゆえに疾走し、時代の罠にはまり込んでしまったのかも知れません。しかし、26歳で刑死するまでのたった10年ほどにも関わらず、彼の生涯は濃密でした。若くして散った他の志士達にしてもそうです。歴史にもしもはありませんが、左内はじめ、そうした志士達が老成し、新政府においてその辣腕を揮ったとすれば、その姿はどんなものだったでしょうか。
ホーム|歴誕カレンダーとは|Web歴誕カレンダー|歴誕通販|れきたんQ&A|個人情報について|通信販売表示
取扱店・プレスリリース|れきたん歴史人物伝|れきたん編集室|れきたん壁紙|リンク|お問い合せ
Copyright (C) 2005 有限会社 秋山ワークス