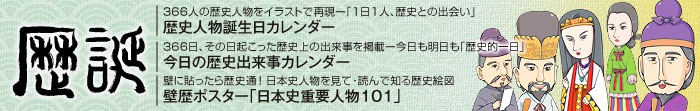

- れきたん歴史人物伝は、歴史上の有名人の誕生日と主な歴史的な出来事を紹介するコーナーです。月に一回程度の割合で更新の予定です。バックナンバーはこのページの最後にまとめてあります。
9月号 2006年9月27日更新 - 【今月の歴史人物】
- 交遊の人
- 正岡子規
慶応3(1867).9.17〜1902.9.19
- 今月号のイラスト

- ◆永遠の野球少年
- (C) イラストレーション:結木さくら
- 9月の主な誕生人物
- 01日アストン/物理学者
- 01日真山青果/小説家
02日伊藤博文/政治家
03日黒板勝美/歴史学者
04日ブルックナー/作曲家
05日ルイ十四世/フランス国王
06日ド−ルトン/化学者、物理学者
07日エリザベス1世/イギリス女王
07日嵯峨天皇/第52代天皇
08日ドヴォルジャーク/作曲家
09日リシュリュー/政治家
09日副島種臣/政治家
10日中橋徳五郎/政治家、実業家
10日バタイユ/思想家、評論家
11日後白河法皇/弟77代天皇
11日ノイマン/物理学者
12日アスキス/政治家
12日徳田球一/社会運動家
13日シューマン/ピアニスト
13日フンボルト/博物学者
14日太宰春台/江戸時代の儒者
15日朱子/学者
15日石田梅岩/心学者
15日岩倉具視/政治家
16日竹久夢二/画家
17日正岡子規/俳人、歌人
17日リーマン/数学者
18日横山大観/画家
18日土屋文明/歌人
19日アンリ3世/フランス国王
20日シンクレア/小説家
21日菱田春草/画家
22日ファラデー/物理学者
22日吉田茂/政治家
22日幸徳秋水/社会運動家
23日オクタヴィアヌス/ローマ帝国皇帝
24日ワレンシュタイン/軍人
24日フィッツジェラルド/小説家
25日石橋湛山/政治家
25日ケッペン/気候学者
26日ハイデガー/哲学者
26日エリオット/詩人
26日ガーシュイン/作曲家
27日ボシュエ/神学者、説教家
27日マハン/軍人、歴史学者
28日メリメ/小説家
28日クレマンソー/政治家
29日徳川慶喜/江戸幕府15弟将軍
29日ネルソン/軍人
29日フェルミ/物理学者
30日ガイガー/物理学者 - 交遊の人
今回紹介するのは近代俳句・短歌の確立者として高名な正岡子規です。子規といえば病に倒れ、大きな才能を持ちながら若くして亡くなった人物ですが、その短い生涯にもかかわらず、後世に名を残すさまざまな面々と交遊を持ったことはご存知でしょうか。さて、子規とはどんな人物だったのでしょう。
文学と政治と幼なじみ
正岡子規は慶応3(1867)年9月17日、松山藩の下級武士の子として生まれました。少年時代から漢詩を作り、小説を読み、同人誌まで制作するなど、文学を好みました。
その一方で子規は政治にも興味を持ちはじめます。折りしも時代は自由民権運動の勃興した頃。松山は運動の根拠地の一つであった高知の近くということもあり、中学生の子規もその波にさらされました。なんと演説会まで開催するほどで、やがて子規は政治家を志し、東京へ上る希望を抱くこととなります。その夢は早晩叶い、16の年に、子規は上京します。
さて、この松山時の幼なじみで親友に秋山真之という人物がいます。子規の上京に刺激され、同じように上京した彼は後に海軍軍人となります。日露戦争における日本海海戦では参謀として作戦の多くを立案し、海戦史上未曾有の大勝利を導く立役者ともなりました。軍人としては珍しく名文家としても知られ、日露戦争での「天気晴朗ナレドモ浪高シ」などの電文は彼が起草したものです。漱石との出会い
上京後、子規は東大予備門へと入学しました。政治家を志していた子規でしたが、それはやがて哲学者への希望となり、そこからさらに文学の道を志向するようになります。俳句を本格的に作り出すのもこの学生時代からです。
この頃の友人関係で見逃せないのは夏目漱石でしょう。後の文豪である漱石は、子規とは同い年で予備門の同級でした。互いの実力を認めあった二人は、よき親友として長く付き合いが続いてゆくこととなります。
余談ですが、子規がベースボールというものを知ったのもこの時代でした。自らの幼名「升(のぼる)」とボールをひっかけ「野球(のボール)」という筆名まで使うほど熱中したようです。この「野球」という筆名は、「野球」という単語が使われた日本で初めての例とされます。病の影
文学に、スポーツに、学生生活を満喫していた子規をトラブルが襲います。喀血です。この喀血を期に、子規は「子規」の筆名を用いはじめます。「子規」とはホトトギスのことであり、ホトトギスとは「血を吐くまで鳴き続ける」と言われる鳥でした。すなわち、ホトトギスと血を吐いた自分をひっかけたわけです。好きだったベースボールも出来なくなりました。また、この頃から後に子規の継承者と言われるようにもなる河東碧梧桐、高浜虚子らへの俳句指導が始まっています。
やがて子規は東京帝国大学へと入学しますが、成績不振のために中退。日本新聞社へと入社します。「日本主義」という言葉まで生んだ新聞「日本」を発行する新聞社で、社長は陸羯南。当時を代表するジャーナリストの一人です。陸は子規の才能を高く評価し、いよいよ子規はこの「日本」や姉妹紙「小日本」を中心にその文学活動を本格的にし、俳句や短歌の世界を革新してゆくこととなります。子規をめぐる人々
日清戦争が勃発すると、子規は従軍記者として大陸へ渡りました。この取材期間中に子規は体調を壊し、帰途の船中において喀血し、帰国後数か月、寝たきりの状態になってしまいます。
それでも何とか回復した子規は、松山に帰郷します。松山には親友である夏目漱石が中学校教師として赴任していました。余り知られていないことですが、この時二人は二か月ほどの共同生活を送りました。子規は郷里の後輩らと共に句作に熱中し、漱石も共に句作しました。
その後、再び上京した子規は病をおして句会を開催。碧梧桐、虚子のほか、漱石、さらにはあの森鴎外まで参加しました。また、松山では句誌「ホトトギス」が創刊され、子規も積極的に参加しました。
また子規は「歌よみに与ふる書」などを発表し、短歌の革新運動にも手を染めました。「(紀)貫之は下手な歌よみ」と古今集以後の和歌を真っ向から否定し、万葉調の和歌を最上としました。彼に共鳴した人々は伊藤左千夫や長塚節。いずれも文壇に確固たる地位を築く人物です。
子規の活動は、いよいよ大きなうねりを生み出しました。それとともに、その病状もついに後戻りの効かないところまで悪化します。しかし、疼痛に耐えながら、子規は死の二日前まで書き続けました。1902(明治35)年9月19日、正岡子規は亡くなりました。35歳という若さでした。
子規の人脈は、子規の没後にさらに輝きを増してゆきます。高浜虚子、河東碧梧桐は子規の後継者として俳壇に大きな流れを生み出してゆきます。すでに本拠を東京に移していた「ホトトギス」の周辺には多くの文人が集まり、「ホトトギス派」と言われる文壇の一大流派を築き上げ、文学史に確かな足跡を残しました。漱石が『吾輩は猫である』を連載したのもこの「ホトトギス」なのです。子規の歌論に共鳴した伊藤左千夫は後に斎藤茂吉などと「アララギ」を創刊、こちらもアララギ派という一流派を形成し歌壇の一角を担ってゆきます。ちなみに、ともに少年時代をすごしたあの秋山真之が日本海海戦に臨むのはは、子規が亡くなった2年半後のことです。
子規の求心力が強過ぎたのか、以後の俳句・短歌が子規に縛られたかのように硬直化したとの批判があることも書き添えておかねばなりませんが、それでも子規の業績は、子規をめぐる多くの人々によって受け継がれ、大きく育ちました。わずか35年の生涯を、多くの仲間とともに駆け抜けた巨人。それが正岡子規でした。
ホーム|歴誕カレンダーとは|Web歴誕カレンダー|歴誕通販|れきたんQ&A|個人情報について|通信販売表示
取扱店・プレスリリース|れきたん歴史人物伝|れきたん編集室|れきたん壁紙|リンク|お問い合せ
Copyright (C) 2005 有限会社 秋山ワークス