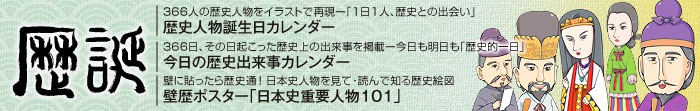
- れきたん歴史人物伝は、歴史上の有名人の誕生日と主な歴史的な出来事を紹介するコーナーです。月に一回程度の割合で更新の予定です。(バックナンバーはこのページの最後にもまとめてあります)
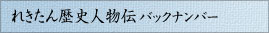
1月号 2010年1月29日更新 - 【今月の歴史人物】
- 吾輩は悩んでいる
- 夏目漱石
慶応3(1867).1.5〜1916.12.9
- 今月号のイラスト

- ◆三四郎書いたの帰国後それからだ門。
- (C) イラストレーション:結木さくら
- 1月の主な誕生人物
- 01日 豊臣秀吉/安土桃山時代の武将
- 01日 フレイザー/人類学者。古典学者
- 01日 クーベルタン/教育者
02日 道元/鎌倉時代の僧
03日 加藤高明/政治家
03日 キケロ/哲学者、政治家
03日 小林一三/実業家
04日 グリム(ヤーコブ)/童話集成家、言語学者
05日 夏目漱石/小説家
06日 ジャンヌダルク/救国の少女
06日 シュリーマン/考古学者
07日 グレゴリウス十三世/ローマ法王
08日 徳川綱吉/江戸幕府5代将軍
08日 堀口大学/詩人、翻訳家
09日 ニクソン/政治家
09日 チャペック/小説家、劇作家
09日 ボーボワール/小説家、評論家
10日 鈴木正三/安土桃山〜江戸時代の武将、僧
10日 高山樗牛/評論家
10日 嶋村抱月/評論家
11日 伊能忠敬/江戸時代の地図作成家
12日 ペスタロッチ/教育者
13日 狩野芳崖/画家
13日 ベルツ/医師
14日 シュバイツァー/医者、神学者
14日 三島由紀夫/小説家
15日 モリエール/劇作家
15日 西條八十/詩人
16日 葛西善蔵/小説家
16日 鳥羽天皇/第74代天皇
16日 伊藤整/小説家、評論家
17日 ロイドジョージ/政治家
18日 モンテスキュー/法学者
19日 森鴎外/小説家
19日 コント/哲学者
19日 ポー/小説家
19日 セザンヌ/画家
20日 岡田啓介/政治家、軍人
21日 上杉謙信/戦国時代の武将
22日 大塩平八郎/江戸時代の儒者、武士
22日 ベーコン/哲学者
23日 マネ/画家
23日 スタンダール/小説家
23日 湯川秀樹/科学者
24日 フリードリヒ大王/プロシア王
24日 ボーマルシェ/劇作家
25日 ボイル/化学者、物理学者
25日 ラグランジュ/数学者
25日 御木本幸吉/実業家
25日 徳富蘇峰/ジャーナリスト
26日 マッカーサー/軍人
27日 モーツァルト/作曲家
27日 前田青邨/画家
28日 スタンリー/探検家
29日 ベルヌーイ(ダニエル)/数学者
29日 チェーホフ/小説家、劇作家
29日 ロラン/小説家、劇作家
30日 勝海舟/江戸時代の幕臣
30日 ルーズベルト(フランクリン)/政治家
31日 シューベルト/作曲家 - 吾輩は悩んでいる
近代の文豪、夏目漱石。極めて知名度の高い歴史人物です。最近までお札の肖像画に選ばれていたこともあり、日本人のほとんどがその名と顔を記憶していると言ってもよいのではないでしょうか。その作品に接した方も多いでしょう。今回はそんな有名人物の生涯を見てみましょう。
不安定な少年時代
夏目漱石は明治維新の前年にあたる慶応3(1867)年の1月5日、江戸の町名主の家に生まれました。町名主というのは江戸の一定区域ごとに置かれた役人の一種で、担当する町内にお触れを回したり、訴えごとの処理を行ったりしました。町名主は武士の身分ではないものの、一般の町人よりは地位が重く、夏目家もそれなりに裕福であったようです。
漱石の本名は「金之助」といいますが、この名付けについてこんなエピソードが伝わっています。漱石が生まれたのは古い暦でいうところの「庚申の日」にあたり、この日に生まれた子は将来大泥棒になるという迷信がありました。そのため、厄よけの効果があるとされた「金」の字を名前に含めたということです。
そんな漱石でしたが、実はその誕生はあまり歓迎されず、1歳の時に養子に出されてしまいます。漱石にはきょうだいが大変多く、両親も高齢で、子供の誕生は家の負担になることなどがその理由だったようです。そもそも漱石が生まれたのは歴史的には明治維新の前年で、世情不安定な時期。これも両親が子供の誕生を負担に思った理由のひとつになりました。
ともかく、こうして漱石は養子に出ました。養子先の両親は漱石を可愛がりましたが、幼い漱石は、血のつながらない親との暮らしに何か違和感のようなものを感じていたようです。その後、養父母は不和によって離婚し、漱石は9歳の時に夏目家へと戻ります。ただしこの時は養父の姓を名乗ったまま。後に夏目姓に戻りますが、それは二十歳も過ぎた頃でした。養父家と実家の対立が原因で姓を戻すのが遅れたとされます。養子先と実家を転々とし、トラブルに振り回されたこれらの経験は、漱石の人格に深い影響を与えたと言われています。後にはこれらの経験を下敷きにした『道草』という小説も書かれました。神経衰弱に悩む
複雑な少年時代を送った漱石でしたが、勉学の方はしっかりとさせてもらっていました。その才能も豊かで、特に漢文学を好みました。しかし後には、兄のすすめもあり、英文学の勉強も始めています。
漱石が「大学予備門」に入学したのは17歳の時です。大学予備門というのは東京大学に入学する前の学生たちが教育を受ける機関。東大の下部機関にあたる学校で、現代の塾や予備校とは違います。東京大学の付属高校というニュアンスがやや近いのですが、当時の教育制度は今とは著しく異なりますので、やはりこれに相当する機関は「今は無い」というのが正確なところです。
さて、その大学予備門において漱石はあの正岡子規と出会っています。のちに近代最大の俳人・歌人と言われるようになる子規は、漱石と同級生でした。漱石と子規はなかなか気が合ったようで、この後も長く付き合いが続いてゆきます。また、漱石というペンネームが使われ出したのもこのころで、それには子規の影響があったとも言われます。ちなみに「漱石」というのは中国の古典に出てくる「漱石枕流(石に漱ぎ(くちすすぎ)、流れに枕す)」という言葉が元で、変人や頑固者といった意味です。
1890年、漱石は東京大学(当時の名称は帝国大学)の英文科に入学しました。漱石の優秀さは凄まじく、全国からエリートが集まる中、予備門から大学卒業まで、ほとんどの年で首席を取ったといいます。
しかし、この頃から漱石をある問題が襲います。それは漱石の伝記においては「神経症」「神経衰弱」などと表現される精神的な不安定でした。
その原因はさまざまあったと言われますが、まず大きかったのは英文学に対する葛藤でした。自分は日本人であるのに、なぜ一生懸命英文学を研究しているのかという疑問は漱石を苦しめたといいます。時代は明治、ちょっと遡れば江戸時代です。日本と外国、古い時代と新しい時代に挟まれる圧力は現代人でも感じることがありますが、漱石の時代のそれは、想像を絶するものだったのかも知れません。
また、この時期、漱石の兄嫁が亡くなるという出来事が起こり、それも神経衰弱の原因のひとつになりました。漱石は彼女に淡い恋心のような憧れを抱いていたと言われており、兄嫁の死は漱石を深く打ちのめしたのです。また、その兄があっと言う間に再婚してしまったことも漱石にとっては二重の打撃でした。
大学を卒業後の漱石は、神経衰弱がますます酷くなり、さらには肺結核にまでかかってしまいます。この時漱石は卒業後に就いた高校教師の職を突然辞め、静養を兼ねて愛媛の松山へ中学校教師として赴任します。また、松山は親友・正岡子規の故郷でもありました。成績不振で大学を辞めた子規は松山に戻っており、漱石と俳句などを作りあったといいます。こうして漱石は、松山滞在によって何とか落ち着きを取り戻しました。ちなみに、この時の経験を活かして書かれた小説が『坊っちゃん』です。結婚と苦しいイギリス留学
その後、漱石は熊本に教師として赴任、結婚します。しかしこの結婚は漱石にとって必ずしもプラスではなかったようです。というのも、漱石の妻というのがこれまた精神的に不安定な人だったからです。結婚の翌年に流産した時は川に身投げを試みたことなどもありました。田舎の環境に馴染めないことなどから、癇癪もよく起こしたといいます。今では漱石の妻と言えば悪妻の代名詞のように使われることもあります。実際にそうだったかは分かりませんが、漱石にとっては気苦労と悩みの多い結婚生活だったことは間違いないようです。
このように、私生活はもうひとつだったものの、学問的、社会的な面では、漱石の人生は順調でした。英文学の教職として実績を重ねており、やがて漱石は英語研究のためにイギリスへ留学せよという国の命令を受けます。
こうして漱石は日本を発ちます。1900年のことでした。ところが、イギリスでも漱石はあの神経衰弱に悩まされることになります。成果を上げようというプレッシャーに立ち向かい、人種差別も経験し、滞在費は欠乏し、その上に例の英文学研究に対する疑問までが首をもたげ、なのに日本の妻は冷たく、イギリス留学中の漱石は最悪の精神状態にまで落ち込みます。日本の文部省には「夏目が狂った」という情報が伝わるほど、それは酷いものでした。ぼろぼろになった漱石は、1903年の初めにようやく帰国します。ついに小説を書く
帰国後、漱石は東大の講師などの職に就くものの、相変わらず家庭は上手く行かず、神経衰弱も回復しませんでした。そんな中、高浜虚子によって気晴らしとしての小説の執筆を勧められます。高浜虚子というのは正岡子規の弟子にあたる俳人です。国語の教科書などには彼の俳句がほとんど間違いなく載っていますから、知っている方も多いでしょう。なお、子規はこの時すでに病によって亡くなっています。
こうして書かれたのが『吾輩は猫である』でした。『吾輩は猫である』は虚子の雑誌『ホトトギス』に載り、大人気となりました。
その後も漱石は精力的に作品を発表します。『坊っちゃん』『草枕』『虞美人草』。前期三部作とされる『三四郎』『それから』『門』。これらの作品を発表する間に漱石はそれまでの生業だった教職を去り、完全な職業作家となりました。気晴らしの小説執筆が実は天職で、やがて漱石を近代史上最高峰の大文豪の地位へと連れていくのですから、分からないものです。
その後、漱石は大病を経験します。神経衰弱の漱石は胃病持ちで、それが極度に悪化したため、伊豆の修善寺温泉で療養します。そして、その地において大吐血するのです。これで漱石は生死の境を彷徨いました。多くの伝記では「修善寺の大患」などと書かれる出来事です。
しかし漱石は何とか回復し、この後も神経衰弱と付き合いつつ小説を書き続けます。大病の後の『彼岸過迄』『行人』『こころ』(後期三部作)はそれまでとは作風の違う傑作とされます。絶筆となったのは『明暗』。この作品を完結させることなく、漱石はこの世を去りました。死因は胃潰瘍の悪化でした。享年49、1916年12月9日のことです。悩める文豪
ここまで文豪・夏目漱石の人生を見てきました。漱石とは、常に悩みとともにある、いかにも繊細な人物だったように思えます。漱石の人生で大変興味深いのは、小説の執筆期間が極めて短いことです。幾多の傑作を残し、文豪といわれる夏目漱石ですが、およそ50年の人生のうち、創作に費やした期間は実は10年強に過ぎないのです。それ以外の期間は学問や教職をし、また、病に苦しみながら悩み続けていたのです。勿体ないことだったという気がする一方、もしこの期間を小説を書くために費やしていたなら、文豪・夏目漱石は生まれていなかったようにも思われますが、はたしてどうだったでしょうか。
ホーム|歴誕カレンダーとは|Web歴誕カレンダー|歴誕通販|れきたんQ&A|個人情報について|通信販売表示
取扱店・プレスリリース|れきたん歴史人物伝|れきたん編集室|れきたん壁紙|リンク|お問い合せ
Copyright (C) 2009 有限会社 秋山ワークス