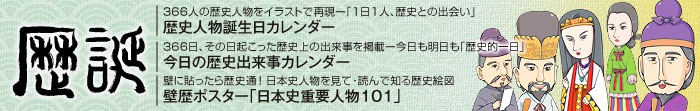
- れきたん歴史人物伝は、歴史上の有名人の誕生日と主な歴史的な出来事を紹介するコーナーです。月に一回程度の割合で更新の予定です。(バックナンバーはこのページの最後にもまとめてあります)
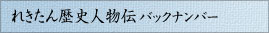
7月号 2010年7月29日更新 - 【今月の歴史人物】
- やるべきことをやっていた
- 緒方洪庵
文化7(1810).7.14〜文久三(1863)6.10
- 今月号のイラスト

- ◆蘭学を教える適塾を洪庵。
- (C) イラストレーション:結木さくら
- 7月の主な誕生人物
01日 ライプニッツ/哲学者、数学者
02日 ヘッセ/小説家、詩人
03日 カフカ/小説家
04日 ガリバルディ/将軍
フォスター/作曲家
05日 コクトー/作家
06日 ホブソン/経済学者
07日 睦奥宗光/政治家
マーラー/作曲家
シャガール/画家
08日 ロックフェラー/実業家
09日 レスピーギ/作曲家
10日 カルヴィン/神学者
ピサロ/画家
プルースト/小説家
11日 穂積陳重/法学者
12日 モディリアーニ/画家
ソロー/作家
13日 森有礼/政治家
14日 緒方洪庵/江戸時代の医師、蘭学者
ミュラー/生物学者
後鳥羽天皇/第82代天皇
15日 レンブラント/画家
国木田独歩/小説家
16日 アムンゼン/探検家
コロー/画家
17日 徳川家光/江戸幕府三代将軍
18日 ローレンツ/物理学者
サッカレー/小説家
内藤湖南/歴史学者
フック/物理学者
19日 ドガ/画家
クローニン/小説家
20日 伊藤仁斎/江戸時代の儒者
21日 ヘミングウェー/小説家
22日 メンデル/植物学者
23日 二宮尊徳/江戸時代の農学者
フィッシャー/哲学者
24日 谷崎潤一郎/小説家
ボリバル/独立運動指導者
デュマ/小説家
25日 バルフォア/政治家
26日 ユング/心理学者
ショー/劇作家
27日 高橋是清/政治家
28日 フォイエルバッハ/哲学者
片山哲/政治家
29日 ハマーショルド/政治家
ムソリーニ/政治家
重光葵/外交官
30日 フォード/実業家
31日 クラーク/教育者家- 柳田国男/民俗学者
- やるべきことをやっていた
今回ご紹介するのは、江戸後期から幕末にかけ、大坂の町を拠点に活躍した医師・教育者の緒方洪庵です。現在では中くらいの知名度といった人物でしょうか。しかし、彼が時代に残した業績は非常に大きなものがありました。
誕生と幼名
緒方洪庵は、文化7(1810)年7月14日、備中国(現在の岡山県)の下級武士の家に誕生しました。父の名は佐伯惟因、幼名は田上●之助(たのかみせいのすけ・●は馬偏に辛)といいました。
生まれた家と姓が違っているのが奇妙ですが、田上というのは佐伯家の別名にあたるため、そう名付けられたという理由のようです。さらに、成長後は先祖にゆかりのある「緒方」の姓に改名しました。また、名の方もたびたび変えています。しかし、ここでは一般に知られる「緒方洪庵」の名で通すことにします。大坂、江戸、長崎で学問
洪庵が16歳になったころ、父の任地が大坂になり、洪庵も大坂に移ります。大坂で洪庵は、中天游という人物の私塾に通います。中天游は大坂で活動していた蘭医・蘭学者で、医学のみならず、西洋のさまざまな学問の知識を持っていました。洪庵は彼のもとで医師をめざすと決意し、医学などの蘭学を熱心に学び始めるのです。のちに洪庵は大坂を拠点として活動してゆくのですが、その基礎が、この時代にできたと言えるでしょう。なお、「緒方」の姓に改名したのはこの頃のことです。
洪庵が天游のもとで学んだ時代はおよそ4年間続きました。こののち洪庵は江戸へと出て、坪井信道という蘭医につき、同じように蘭学を学びました。この頃には洪庵の実力はかなりのものになっていたようで、医書の翻訳なども手がけています。この江戸での学問もおおよそ4年ほど続きました。
江戸での学問を終えた洪庵は、一度故郷の備中に帰ります。ところが、帰郷後、師の中天游が亡くなったという知らせが飛び込んできます。洪庵は大坂へと出て、師の遺した塾などを再び安定するまで手伝ったということです。洪庵の性格、そして天游への思いが伝わってくるエピソードです。
さて、そのようなことがあってから、今度は洪庵は長崎へ行きます。蘭学の本場とも言える長崎で洪庵は、さらに自らの学問を高めました。「適塾」と塾生たち
大坂、江戸、長崎と修行した洪庵は、一時帰郷を挟んで、学問上のふるさととも言える大坂へと再び戻り、自らの蘭学塾を開塾します。これが有名な「適塾(適々斎塾)」です。洪庵28歳の年でした。
医師だった洪庵が開いたものですので、適塾ははじめ医学中心の塾をめざしたようです。しかし、徐々にその色は薄まり、適塾は蘭学の基礎教育を重視する塾となってゆきます。
その理由は、世情の変化にありました。洪庵が塾を開いたのは、まさにペリー来航前夜と言える時代です。蘭学を通して世界の変化を感じ取っていた洪庵は、世界のことを理解できる幅広い人材を育てたいと考えました。それで、塾のスタイルを変化させていったのです。
こうして、適塾にはさまざまな人材が集まるようになりました。その中には、のちに有名になる人物が多くいました。
塾生の中でダントツの有名人といえば、やはり福沢諭吉でしょう。豊前出身の諭吉は適塾で蘭学を学び、のちに江戸へ出て、海外留学も経験し、やがて時代を代表する思想家・教育者となります。
長州藩士の大村益次郎も、若き日を適塾で過ごした有名人物です。長州征伐や戊辰戦争を戦略面で支え、新政府における最初期の陸軍政策も担ったことで知られています。
ほかにも、すぐれた開明派だったものの、安政の大獄で刑死した橋本左内、箱館戦争の幹部であり維新後は政府の役職などにも就いた大鳥圭介、同じく箱館戦争に軍医として参加し、維新後は窮民医療の分野で多大な業績を残した高松凌雲らが、適塾出身者として有名です。医師としての洪庵
むろん洪庵は、塾の運営をしながら医師としての活動も行いました。有名な業績としては、種痘の普及活動があります。ジェンナーの回でも少し触れましたが、この時期、長崎の医師・楢林宗建とオランダ人医師モーニッケの二人が、牛痘接種に成功し、それによって得られた種が京都へと持ち込まれていました。それを洪庵が何とか手に入れ、種痘のための施設「除痘館」を開き、大坂での種痘を開始したのです。
具体的な活動は始まったものの、当初は種痘に対する社会の理解が低く、人々に種痘を受けてもらうことさえ非常な苦労がかかりました。種痘事業が軌道に乗るまでは数年ほどを費やしたといいます。しかし、種痘開始のおよそ10年後には、除痘館は幕府に認められ、日本初の公的な種痘施設にまでなりました。
また、洪庵はコレラ治療にも尽力したことが伝わっています。コレラというのはコレラ菌によって引き起こされる伝染病で、当時はたびたび大流行し、恐れられていました。除痘館が公認された安政5年は、コレラが大流行した年でした。この時、洪庵は必死の努力で患者を診察し続け、同時に、コレラ治療に関する手引書を出版して医師らに配るということまで行っています。洪庵はもともと身体の強くなかったこともあり、過労で体調を崩すほどだったといいます。あっけない死
これらの活動を通して、緒方洪庵の名は大変に高まりました。文久二(1862)年には幕府の奥医師(将軍やその家族を診察する医師)になり、上位の医師である「法眼」にも叙せられました。また、幕府の機関である西洋医学所の頭取にも任ぜられました。
しかし洪庵は、文久三年6月10日、喀血してあっけなく亡くなるのです。江戸入りから一年も経たない時期でした。江戸での洪庵は栄達を果たしたとは言え、暮らしは決して楽しいものではありませんでした。むしろ、地位に伴う気苦労や経済的な苦労が絶えなかったといいます。そもそも江戸行きについては、洪庵自身、それほど気乗りのするものではなく、それらのストレスが洪庵の命を縮めたとも言われます。緒方洪庵の成したこと
緒方洪庵という人物は、幕末に生きた人物ではあるものの、政治向きの活動はほとんど行っていません。それゆえ、政治史が軸となる幕末においてはやや地味な存在です。
しかし、洪庵が時代に与えた影響は、やはり大きなものがあります。教育者として多くの開明的な人材を育てたことは、明治維新のひとつの原動力となったと言ってよいでしょう。医師としても、種痘事業をはじめ、非常に充実した業績を残しています。攘夷だ開国だと騒がしかった世情の中、それに浮かされることなく、どっかりと腰を据えて自らのやるべきことをやったという印象です。それこそが、緒方洪庵という人物の爽やかさ、偉大さなのではないでしょうか。
ホーム|歴誕カレンダーとは|Web歴誕カレンダー|歴誕通販|れきたんQ&A|個人情報について|通信販売表示
取扱店・プレスリリース|れきたん歴史人物伝|れきたん編集室|れきたん壁紙|リンク|お問い合せ
Copyright (C) 2010 有限会社 秋山ワークス