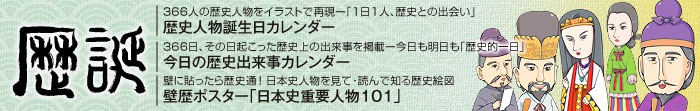
- れきたん歴史人物伝は、歴史上の有名人の誕生日と主な歴史的な出来事を紹介するコーナーです。月に一回程度の割合で更新の予定です。(バックナンバーはこのページの最後にもまとめてあります)
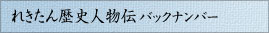
1月号 2011年1月28日更新 - 【今月の歴史人物】
- 「大王」になった文化系王子
- フリードリヒ大王
1712.1.24〜1786.8.17
- 今月号のイラスト
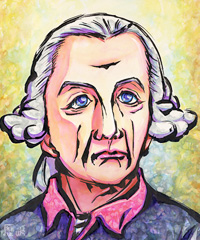
- ◆この宿を出れば私はフリーどりひ!
- (C) イラストレーション:結木さくら
- 1月の主な誕生人物
- 01日 豊臣秀吉/安土桃山時代の武将
- 01日 フレイザー/人類学者。古典学者
- 01日 クーベルタン/教育者
02日 道元/鎌倉時代の僧
03日 加藤高明/政治家
03日 キケロ/哲学者、政治家
03日 小林一三/実業家
04日 グリム(ヤーコブ)/童話集成家、言語学者
05日 夏目漱石/小説家
06日 ジャンヌダルク/救国の少女
06日 シュリーマン/考古学者
07日 グレゴリウス十三世/ローマ法王
08日 徳川綱吉/江戸幕府5代将軍
08日 堀口大学/詩人、翻訳家
09日 ニクソン/政治家
09日 チャペック/小説家、劇作家
09日 ボーボワール/小説家、評論家
10日 鈴木正三/安土桃山〜江戸時代の武将、僧
10日 高山樗牛/評論家
10日 嶋村抱月/評論家
11日 伊能忠敬/江戸時代の地図作成家
12日 ペスタロッチ/教育者
13日 狩野芳崖/画家
13日 ベルツ/医師
14日 シュバイツァー/医者、神学者
14日 三島由紀夫/小説家
15日 モリエール/劇作家
15日 西條八十/詩人
16日 葛西善蔵/小説家
16日 鳥羽天皇/第74代天皇
16日 伊藤整/小説家、評論家
17日 ロイドジョージ/政治家
18日 モンテスキュー/法学者
19日 森鴎外/小説家
19日 コント/哲学者
19日 ポー/小説家
19日 セザンヌ/画家
20日 岡田啓介/政治家、軍人
21日 上杉謙信/戦国時代の武将
22日 大塩平八郎/江戸時代の儒者、武士
22日 ベーコン/哲学者
23日 マネ/画家
23日 スタンダール/小説家
23日 湯川秀樹/科学者
24日 フリードリヒ大王/プロシア王
24日 ボーマルシェ/劇作家
25日 ボイル/化学者、物理学者
25日 ラグランジュ/数学者
25日 御木本幸吉/実業家
25日 徳富蘇峰/ジャーナリスト
26日 マッカーサー/軍人
27日 モーツァルト/作曲家
27日 前田青邨/画家
28日 スタンリー/探検家
29日 ベルヌーイ(ダニエル)/数学者
29日 チェーホフ/小説家、劇作家
29日 ロラン/小説家、劇作家
30日 勝海舟/江戸時代の幕臣
30日 ルーズベルト(フランクリン)/政治家
31日 シューベルト/作曲家 - 「大王」になった文化系王子
今回ご紹介するのは、18世紀のプロシア国王・フリードリヒ大王。正式にはフリードリヒ2世といいますが、「大王」の名の方が通りがよいでしょう。卓越した手腕によってプロシアを強国の地位にまで引き上げたことから、この名で呼ばれるようになりました。
文化系王子
フリードリヒ大王は、プロシア王のフリードリヒ・ヴィルヘルム1世の三男として、1712年1月24日、ベルリンで誕生しました。二人の兄は早くに死んでおり、フリードリヒが父の後継ぎということはすでに決定していました。
プロシアというのは、プロシャ、プロイセンなどともいい、現在のドイツ北方あたりに存在した国です。かつてはそれほど力もなく、そもそもきちんとした国ですらない領域だったのですが、フリードリヒの祖父の代の頃から力をつけ始めました。フリードリヒの父王もプロシア強化に大いに貢献しており、とくに軍事面での手腕が優れていたとされます。
ところが、そんな父王と息子・フリードリヒは、まったくそりの合わない親子でした。父王は厳格、強引で絵に描いたような軍人気質を持っていたのですが、王子フリードリヒはと言うと、音楽や書物を好む文化系の性格だったのです。
父王はそんな息子に我慢ならなかったようで、軍人気質を叩き込もうと我が子に厳しく接し、それは時に暴力に及ぶほどだったといいます。発展中の国を率いるというのは大変なことで、父王も王子をそれにふさわしい人物に育てようと必死だったのかも知れません。しかし、そんな毎日に耐え切れず、フリードリヒはとうとう爆発してしまいます。18歳の時、フリードリヒは父王のもとを逃げ出そうとするのです。逃亡事件
その時、父王とフリードリヒは旅行中で、逃げ出すタイミングとしてはぴったりでした。フリードリヒは仲の良い側近の軍人に協力を頼み、宿を脱走しようとします。しかしこの計画は露見し、フリードリヒも、協力した軍人も捕まりました。まもなくこの軍人は、フリードリヒの見ている前で処刑されました。文字通りの見せしめでした。
この件について父王は全く苛烈で、フリードリヒさえも処刑されかかったといいますが、それはさすがに実行されていません。その後、フリードリヒも観念したのか、父王に許しを請うて和解するのです。
以後、フリードリヒは一つ腰の据わったようになり、国務にも精を出すようになりました。こういう経験をすると、普通は拗ねて歪んだ人格になってもおかしくないのでしょうが、フリードリヒはそうなりませんでした。不思議にも思えますが、歴史に残る人間というのは、そういうものなのかも知れません。
しかしながら、フリードリヒが文化系の気質を全て捨ててしまったわけでもありません。やはり読書を好み、哲学や政治学の素養を高め、自ら執筆なども行っています。当時の著名な哲学者のボルテールと文通していたことは有名な話です。父王との和解が、これらの自由をもたらしたとも言えるでしょう。啓蒙専制君主フリードリヒ
父王の死に伴い、フリードリヒは28歳の時に即位しました。
王としてのフリードリヒは「啓蒙専制君主」の代表格と言われます。「啓蒙」は「啓蒙思想」の「啓蒙」です。啓蒙思想とはごく大ざっぱに言うと、迷信や非理性的な考え方を捨て、人間の持つ理性に従ってものごとを考えましょう、という思想で、現代の民主政治にもつながってゆくものです。教科書などにも必ず出てくる西洋史のキーワードの一つなので、ご記憶にある方も多いと思われます。
では「啓蒙専制君主」はと言うと、読んで字のごとく、啓蒙的な思想に影響された専制君主のことを言います。かれらは王としての絶対的権力を維持しつつ、古い社会構造を改革し、国家・国民の近代化をはかりました。むろんフリードリヒもそうで、即位後は啓蒙思想的な改革政治を推進し、学問も大いに奨励しています。
これより前、絶対王政の時代を代表する君主・フランスのルイ14世は「朕は国家なり」という言葉を残しましたが、フリードリヒは「王は国家第一の下僕」という言葉を残しました。ここに啓蒙専制君主の特徴が現れていると言ってよいでしょうか。シュレジエン強奪
近代的な思想にも影響される一方、啓蒙専制君主はあくまでも専制君主です。フリードリヒは国内の改革を行いながら、父王ゆずりの軍人的側面も存分に発揮してゆきます。フリードリヒは父王の残した強力な軍隊をさらに増強し、周囲への領土的野心もむき出しにします。フリードリヒが狙ったのは、プロシアの南にあるシュレジエンという地域でした。
当時のシュレジエンはオーストリアが保有していました。オーストリアは当時ヨーロッパ有数の大国。ハプスブルク家という大貴族が治めていましたが、この頃、そのハプスブルク家の当主が死去します。しかし、男子の後継者がおらず、跡を女子が継ぐことになりました。これがマリア・テレジアで、きわめて有能な女帝として歴史に名を残すことになる人物です。
ところが、この継承を認めようとしない国がいくつもありました。女子による相続に問題あり、というのが大きな理由でしたが、それと同時に、この機会を利用してオーストリアの力を削ぎ落としたいという各国の思惑もありました。
そしてフリードリヒもこの情勢に乗ります。プロシア軍はシュレジエンに侵入すると、オーストリア軍を打ち破り、シュレジエンの奪取に成功します。その後、いくつかの戦闘を経て、プロシアによるシュレジエンの保有をオーストリアに認めさせました。
なお、オーストリアは、ほかにもフランスをはじめとする各国と、ほうぼうで戦いを繰り広げています。これらをまとめてオーストリア継承戦争といいますが、この戦争において目立った利益を上げたのはフリードリヒのプロシアくらいで、他の国々はほとんどが空振りの骨折り損でした。フリードリヒの手腕は際立っていたのです。滅亡寸前の苦境
ともかく、プロシアは勢力拡大に成功しました。しかし、これでおさまらないのがオーストリアです。戦後、およそ10年ほどの平和な期間を経て、オーストリアとプロシアは再び戦火を交えます。これを七年戦争といいます。
オーストリアは七年戦争に先立ち、フランスとロシアという強国を味方につけました。なかでも、きわめて仲の悪かった2か国、フランスとオーストリアの同盟は衝撃的で、『外交革命』と呼ばれるほどの出来事になりました。むろんこのことはフリードリヒにとっても計算外で、戦争は始めたものの、墺仏露という3強国を敵に回したプロシアは徐々に追い詰められ、ついには国家存亡の危機にまで陥り、フリードリヒ自身も本気で自殺を考えるほど追い詰められたといいます。大国オーストリアとマリア・テレジアの力を見せつけられた格好です。
しかし、ここでフリードリヒに幸運が舞い込みます。それは、ロシアの女帝・エリザベータの死でした。代わって皇位についたピョートル3世がフリードリヒの信奉者、いわば「ファン」のようなものであったため、プロシアはロシアと停戦することができたのです。かくして3強の一角は崩れ、プロシアは助かり、シュレジエンの保有存続もかなうことになりました。
それにしてもここまでの流れ、フリードリヒに都合のいいことといったらありません。フリードリヒという人物は、実力と同時に運も兼ね備えていたとしか言いようがないでしょう。その晩年
その後、フリードリヒは、戦争で疲弊したプロシアの復興に力を尽くします。外交についても、勢力の維持・拡大を目指しはしましたが、七年戦争のような大戦争に踏み込むことは避け、慎重に立ち回りました。
こうして名実共にプロシアを強国へと押し上げたフリードリヒが亡くなったのは、1786年8月17日のことでした。偉大な王も晩年は気難しくなり、孤独の中に沈みがちだったといいます。
フリードリヒの死後まもなく、フランス革命が発生し、以後、西洋世界は市民革命の大波をかぶります。フリードリヒがその典型とされる「啓蒙専制君主」の政治も、もはや時代に合わないものになっていました。
ホーム|歴誕カレンダーとは|Web歴誕カレンダー|歴誕通販|れきたんQ&A|個人情報について|通信販売表示
取扱店・プレスリリース|れきたん歴史人物伝|れきたん編集室|れきたん壁紙|リンク|お問い合せ
Copyright (C) 2010 有限会社 秋山ワークス