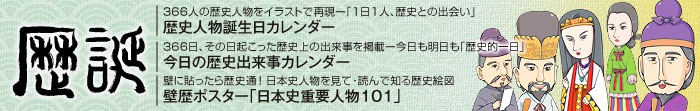
- れきたん歴史人物伝は、歴史上の有名人の誕生日と主な歴史的な出来事を紹介するコーナーです。月に一回程度の割合で更新の予定です。(バックナンバーはこのページの最後にもまとめてあります)
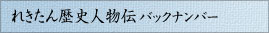
5月号 2012年05月31日更新 - 【今月の歴史人物】
- 大権力によって危機に対処
- 北条時宗
建長3(1251).5.15〜弘安7(1284).4.4
- 今月号のイラスト

- ◆元冦に立ち向かう時むね。
- (C) イラストレーション:結木さくら
- 5月の主な誕生人物
- 01日 円山応挙/江戸時代の画家
02日 エカテリーナ二世/ロシア女帝
03日 マキァベリ/政治家、歴史家
04日 西郷従道/政治家
05日 小林一茶/江戸時代の俳人
05日 キルケゴール/哲学者
05日 高野長英/医師、蘭学者
05日 マルクス/経済学者
06日 フロイト/精神医学者
06日 ロベスピエール/革命家
07日 本居宣長/江戸時代の国学者
07日 ブラームス/作曲家
07日 美濃部達吉/法学者
07日 ブラウニング/詩人
08日 トルーマン/政治家
09日 バリー/劇作家
10日 モンジュ/数学者
10日 ブライス/法学者、政治家
11日 ダリ/画家
11日 ファインマン/物理学者
12日 ナイチンゲール/看護婦
12日 武者小路実篤/小説家
13日 マリア・テレジア/オーストラリア女帝
13日 カルノー/軍人、政治家
14日 北条時頼/鎌倉幕府五代執権
14日 ファーレンハイト/技術者
14日 オーウェン/思想家
15日 北条時宗/鎌倉幕府八代執権
15日 メッテルニヒ/政治家
15日 キュリー(ピエール)/物理学者
15日 市川房枝/政治家
16日 間部詮房/江戸時代の側用人
16日 ヒューズ/発明家
17日 ジェンナー/医学者
17日 サティ/作曲家
17日 安井曾太郎/画家
18日 ラッセル/数学者、哲学者
19日 西田幾太郎/哲学者
19日 フィヒテ/哲学者
20日 バルザック/小説家
20日 ミル(ジョン・スチュアート)/経済学者、思想家
21日 デューラー/画家
21日 ルソー/画家
22日 ドイル/小説家
22日 ワグナー/作曲家
22日 坪井逍遥/小説家
23日 リンネ/植物学者
23日 リリエンタール/技術者、発明家
24日 ビクトリア/イギリス女王
24日 ハチャトゥリアン/作曲家
25日 エマーソン/哲学者、詩人
25日 チトー/政治家
26日 中村正直/教育者
26日 ガイスラー/技術者
27日 イブン・ハルドゥン/歴史家
28日 崇徳天皇/第75代天皇
28日 ピット(小ピット)/政治家
28日 ギヨタン/医師
29日 林鵞峯/江戸時代の儒者
29日 ケネディ/政治家
30日 林房雄/小説家
31日 ホイットマン/詩人 - 大権力によって危機に対処
今月ご紹介するのは鎌倉幕府の8代目執権・北条時宗。かつてNHKの大河ドラマにもなったため、それでご存知の方も多いでしょう。将来のリーダーとして育ち、その通りに権力を手中にし、元寇などの国家的危難に対処した人物です。
将来のリーダー
北条時宗は建長3(1251)年5月15日に生まれました。父は5代目執権の北条時頼。幕府内での対立勢力を抑え、政治機構も改革するなど、すぐれた実績を残したと評価される人物です。
時宗には時輔という兄がいましたが、かれは側室の子でした。それに対して時宗は正室の子でしたから、幼い頃から時頼の後継者として育てられることになりました。
時宗の元服は6歳の時です。烏帽子親は鎌倉幕府初の皇族出身将軍(宮将軍)である宗尊親王。烏帽子親とは、元服時におく「儀式上の親」とでも表現すればよいでしょうか。なお、時宗の宗の字は親王から貰ったものです。
話が前後しますが、父の時頼は時宗の元服前に執権を退いており、その立場で政務を取り仕切っていました。時頼の後の執権には北条長時という人物が就任していましたが、これは時宗に力がつくまでの中継ぎといった様子です。
9歳になると時宗は幕府の「小侍所」に入ります。小侍所とは、将軍の側に仕え、警備などを仕切る機関。当時の別当(長官)は北条一族の重要人物だった北条実時でしたが、時宗もまた別当待遇で小侍所に入りました。ツートップ体制というわけですが、実はこれ以前に小侍所の別当が2人であったことはなく、これが初の例です。将来のリーダーとしての政治的センスを養うためのはからいだったとされ、時宗がどれほど特別な存在だったかがうかがい知れます。
以後の時宗は、10歳で有力御家人の娘と結婚し、父・時頼が亡くなると13歳で連署(執権を補佐する重職)に就任しました。まさにエリート街道を歩んだというところでしょうか。執権と得宗
さて、ここで「執権」という言葉について少し触れておきましょう。これは鎌倉幕府においては役職の一つです。幕府の政治を仕切る責任者としてあり、源頼朝に連なる源氏の将軍が3代で絶えてからは、事実上の幕府トップとして権力をふるいました。このような形の政治がいわゆる「執権政治」です。これらの内容は学校の歴史の授業でも必ず習うので、ご記憶にある方も多いでしょう。
しかし、ここで一つ引っ掛かりが生まれます。先ほども述べた通り、時宗の父・北条時頼は、途中で執権を退きながら、その後も政治に深く関わっていました。このケースはどうなのでしょう。これは執権政治の形から少々離れてしまっているのではないでしょうか。
実は鎌倉時代も進んでくると、執権というより「北条氏のトップ(本家の相続者)」に権力が集まるような形が強くなってきます。北条一族のトップを「得宗(とくそう)」と呼ぶため、この政治の形を「得宗専制政治」といいます。時頼のケースは得宗専制政治の形態がはっきりと現れてきた一つの大きな例でした。そしてその息子・時宗は、この得宗専制政治の形をさらに確立させていった人物なのです。
いよいよ執権に
連署となった時宗は本格的に政務に関わり始めます。15歳の時には将軍・宗尊親王を謀反の疑いありとして将軍職から追放しました。当時の執権・北条政村や先ほども登場した北条実時、有力御家人の安達泰盛(時宗の妻の兄)らと協力の上で行ったことです。これは親王そのものへの警戒というより、親王を核として反得宗勢力が結合してゆくことを警戒したためでした。一歩も二歩も先読みをした注意深い措置といえます。
その2年後、時宗は満を持して執権となりました。前執権の北条政村が補佐役の連署になっており、万全の布陣だったと言えます。そしてさらにその4年後、つまり執権・時宗が21歳の時に、かれの政治姿勢を象徴するかのような事件が起きます。
その事件は「二月騒動」といい、平たく言えば反得宗勢力の粛清事件です。この時に時宗は、北条氏の傍流である名越時章・教時兄弟、さらには冒頭で少し触れた兄・時輔らを殺害したのでした。これによって北条氏の力は、得宗で執権の時宗に一本化されたのです。
時宗やそれを支える人々がなぜここまで権力固めに腐心したか。それは単なる保身という意味合いだけではなく、眼前に迫っていた国際的問題へ対処する目的もありました。それこそがモンゴルによる日本への圧力です。
この時期、皇帝フビライの国書を携えたモンゴルからの使節が来日していました。国書の内容は、日本に対してモンゴルとの通交を求めるものでした。このコンタクトは数度にわたったものの、日本側はこれを侵略の前兆ととらえ、黙殺しつつモンゴル軍の襲来に備えました。最初に使節がやってきたのは時宗が執権になる前のことであり、その後、時宗は執権に就任します。時宗の執権就任は規定路線であったと同時に、対モンゴルのための体制強化という意味合いもあったのです。その延長に、二月騒動もあったというわけです。元の襲来
日本からの返事がないため、皇帝フビライは日本への侵攻を決定します。元(=モンゴル。侵攻の少し前の時期に国号を変更した)の侵攻は2度にわたりました。現代では、一度目の襲来を「文永の役」、二度目の襲来を「弘安の役」、両方を合わせて「元寇」あるいは「蒙古襲来」などと呼びます。
1度目の襲来は文永11(1274)年のこと。時宗は23歳でした。日本軍は未知の敵・元軍(正確には元と高麗の連合軍)に大いに苦戦するものの、どうにか撃退に成功します。なお、この時「神風」と呼ばれる暴風雨によって元軍が潰滅したという話がよく知られていますが、これは「戦闘中」の話ではなく、すでに撤退した元軍を暴風雨が襲い、潰滅させたということのようです。
戦後、元はまたもや日本へと使節を送ってきます。しかし日本側はこの使節を処刑しました。むろん時宗の決断だったでしょう。元はさらにもう一度使節を送ってきますが、日本側はやはり処刑しています。このようなこともあり、元軍の再度の襲来は必至となりました。
2度目の襲来は弘安4(1281)年のことで、この時は前回の経験を活かして充分に防備を固めていた上に、台風によって元軍がダメージを受けたこともあり、再びの撃退がかないました。問題山積の中、この世を去る
しかしながら、戦後の状況も決して楽観できるものではありませんでした。2度にわたる元との戦いは、幕府を大いに疲弊させていました。しかもこの戦いは、得るもののない対外防衛戦争でした。戦った御家人たちには充分な恩賞も与えられなかったため、かれらの不満は募りました。そして、元の3度目の来襲という問題もありました。もちろん未来の私たちは3度目の元来襲などなかったことを知っていますが、当時の人にはそんなことはわかるはずもありません。幕府としては、元来襲に備えて力を使わざるを得なかったのです。
そんな状況の中、幕府の内部にも軋みは生まれていました。この頃には時宗=得宗に集まった権力は強大となり、北条氏主流とその家来たちが幕政を牛耳るようになっていたからです。それ以外の御家人はここでも不満を募らせました。
そして、これら問題山積の状況の中、時宗はあっけなく病死するのです。死去時、33歳。当時にあってもあまりに若い死です。数々の難問に心と身体を削りつくした結果であったろうと思えます。
時宗は仏教、中でも禅宗を深く信仰している人物でもありました。元寇の最中は、大陸出身の禅僧らの言葉を聞いて精神的な支えともし、元寇後、戦没者を弔うなどの目的で円覚寺という寺を創建もしています。死に際しても信仰心は変わらず、弘安7(1284)年の4月4日、死のまさに当日に出家したと伝わっています。
ホーム|歴誕カレンダーとは|Web歴誕カレンダー|歴誕通販|れきたんQ&A|個人情報について|通信販売表示
取扱店・プレスリリース|れきたん歴史人物伝|れきたん編集室|れきたん壁紙|リンク|お問い合せ
Copyright (C) 2012 有限会社 秋山ワークス